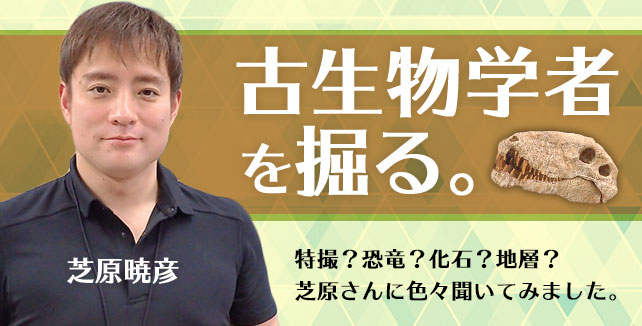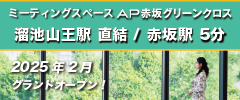働き方・生き方
LIFESTYLE ライフ・スタイル
芝原暁彦 – 古生物学者を掘る。
「特撮の地球科学」の著者、芝原暁彦とは?
特撮戦隊モノ好きが転じて、科学的に特撮を分析した本まで出版してしまう一風変わった古生物学者の芝原さん。しかし古生物学者ってなんなんだろう?何をしているの?どんな仕事なの?古いものを調べると何がわかるの?など、興味が溢れたノビテクマガジン編集部丸岡が、あれやこれやを聞いてみました。
芝原 暁彦(しばはら あきひこ)

古生物学・古環境学、地球科学情報の「見える化」技術など、アカデミックなフィールドで知見を深め、メーカーへの技術移転や科学番組を監修。縦横無尽にカルチャーを闊歩するイノベーション人材。
いつから古生物(化石)に興味があったか
丸岡
今日は、よろしくお願いいたします。実は、先日お会いして、その後とても興味を持ってしまいまして、芝原さんの著書『特撮の地球科学 古生物学者のスーパー科学考察』(イースト・プレス)を購入してしまいました。
本の内容なんですが、「ゴジラの近くに、作戦本部があって危なくない!?」とか、「なぜ、スーパー戦隊はいつも岩場で闘うのか!」、「ウルトラマンって、未来なの?現代なの?」といった、戦隊モノや特撮モノを見て、誰しもが一度は疑問に思ったことを、古生物学者的な見解で解説されていて、とても面白かったです!
芝原
ありがとうございます。
丸岡
それで、こんなことまで解説できる古生物学ってすごいけど、古生物ってなんだろう?なにを研究しているの?そもそも芝原さんって何者!?と思いまして。今日は芝原さんのお話をうかがいたいと考えています。
芝原
はい。よろしくお願いいたします。
丸岡
そもそもの疑問なんですが、古生物って「古」という漢字にもあるとおり、化石とか古いものを調べていらっしゃるんですよね?でも、古いことを調べると何がいいの?という疑問があります。古いことを調べると、現在のどんなことに役に立つのかな?と。だって古いんでしょ?そういうことを本日はうかがいたいと考えています。
芝原さんって、もともとこういう研究をずっとされてきたんでしょうか?
芝原
そもそも、僕は出身が福井だったこともあり、4歳ぐらいから化石を掘り始めていて……

化石発掘は4歳から。
丸岡
え!?(笑)化石がそんな身近にあったんですか?
芝原
化石少年あるあるなんですけど、最初、自分家の庭を掘るんですよ。でも、昨夜に食べた鯵の骨とかしか出てこないわけです。(笑)
それで、化石は身近にないっていうことを、4歳ぐらいで知ったんですね。
丸岡
(笑)
芝原
これは化石じゃないなって思って。(笑)でも、それが大事な気づきで。じゃあ化石って何なんだろう?とか、どこにあるんだろう?って思ったんです。自分の周りを掘っても、住宅街ではなかなか出てこない。実は、もっと深く掘れば出てくるんですけど、子供の力では難しいから。近所で出てこないなら、崖が出てる山の中なら出てくるのか?とか、昔の地層が表面に出てる場所にならあるのでは?と。
つまり場所ごとに埋まってるものが違うんだっていうのが、大体それぐらいで分かったわけなんですよね。で、6歳ぐらいから地元の博物館に通いだして、そこの学芸員さんとかにいろいろ教えてもらって。
丸岡
6歳で学芸員さんに質問を!?早いですね!
芝原
結構6歳ぐらいから、ぼちぼちそういう子が出てきますよね。
丸岡
確かに、わたしの子供の保育園でも車が大好きすぎて、遠足とかで駐車場を通ると、全部車種名と値段を言っている子がいました。特に、中古車販売のチラシが大好きらしくて。値段まで覚えているという。(笑)芝原さんは、そういう感じの化石版の子だったんですね?
芝原
そうですね。電子工作や漫画を書くのも好きだったので、色々やりつつメインが化石だった子供でしたね。あと、パソコンオタクだったので、プログラミングと言っていいようなレベルかわかんないですけど、古いパソコンでガチャガチャいじってコード書いたりとか。中学生ぐらいからは、今やってるような3次元グラフィックのはしりみたいなものをやりだしていましたね。
丸岡
えぇ、すごい。芝原さんが16歳くらいの当時って、インターネットありましたっけ?
芝原
Windows95が出たのが、僕が高3の時ですから、それまではパソコン通信とか。小学校3年くらいにはPC-9801を使っていましたね。
丸岡
フロッピー2枚入れて起動するやつですよね?
芝原
そうそう、フロッピー2枚ガチャンガチャンって入れて起動するやつです。
丸岡
その当時、お家にPCがあるのってすごいですよね。
芝原
父親が言語学の研究をしていたのですが、研究にパソコン使っていたので、それをたまに借りて……という流れで使っていました。
最初は、パソコンに付いてくる辞書みたいに厚いプログラミングの本に書いてあることを、一個一個打ち込んでいました。高校ぐらいになってからは、自由研究で地元の地層を調べていました。福井県の海岸に出て、地層の厚さとか傾きとかをパソコンに入れて計算させる……みたいな事をやっていました。

当時からパソコンを地層の計算に使っていた。
もはやライフワークの地層と化石の魅力とは
丸岡
小さい頃からの地層と化石への愛情というのは、なくならなかったんですか?
芝原
なくならなかったですね~。
丸岡
どこにそんなに魅力があったのでしょうか?
芝原
我ながら地味な事やってたな(笑)と思うんですけど、4歳の時に父親に上野の国立科学博物館に連れてかれたんですね。科学博物館の入口に入ったら、すぐそこにはタルボサウルスっていう、全身12メートル
くらいのでっかい恐竜がいたんですよね。あれにもう、ガツーンとやられちゃって。
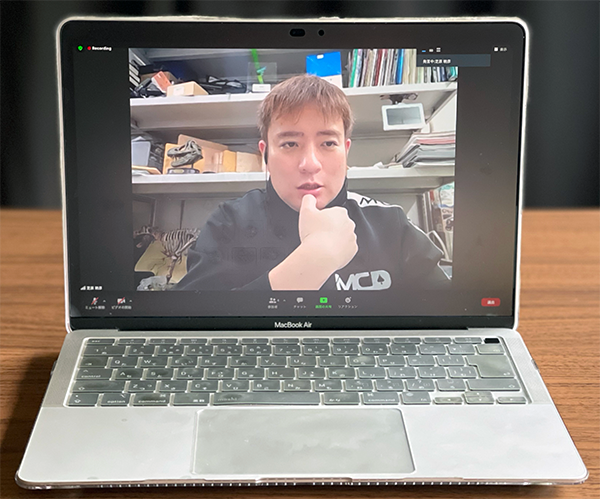
タルボサウルスにガツンとやられる。
丸岡
土を掘ると恐竜が出てくる。だから土掘ろうと。(笑)
芝原
これが地下に埋まっているのか!と思って。(笑)
丸岡
それで、埋まってるところを探そう、どうやら普通の地面には埋まってないらしい、地面には地層というものがあるらしい、地層のどこら辺に埋まってるのか気になる……みたいな流れなんで、どんどんはまってしまったんですか?
芝原
福井って、その辺、ガチ勢が多くてですね。福井県の福井県立博物館が家のすぐ近くにあったんですけど、6歳の時にそこで色々教えて下さったのが、後に恐竜博物館の館長さんになる方なんですよ。当時まだ30代で。たまたま早いタイミングで、そういう人と出会って。
ちょうど僕が生まれた頃から、福井で恐竜が見つかり出して。福井県としても、「これは将来的に観光資源になるな」と判断してくれたんだと思うんですけど、化石に関してかなり異例の予算を投下してくれて。平成元年ぐらいからもう、ガンガン掘り出したんですよね。
そうすると世界中から、最先端の恐竜研究者が集まってくるんです。福井の博物館に、教科書にしか載ってないような人たちがズラっているんですよ。なんか普通にお茶飲んで、議論しているんです。そこに子供の立場を利用して入り込んだんですね。毎日。(笑)「今、最新の研究はどんな感じなのか?」っていうの聞いていました。
だから、インターネットよりも、現実の博物館の方がよっぽど濃密な体験ができたわけです。
地学は地球のビックデータを分析する仕事
丸岡
それは熱が冷めないわけですね。同じようにはまっていたお友達とかがいたと思うんですが、芝原さんみたいにずっと興味を持ち続けていた人はいるんですか?
芝原
僕の同学年ではいなかったんですが、例えば、恐竜研究者でよくテレビに出てらっしゃる先生が、僕の地元にある小中高の6つ上の先輩なんです。
あと、よく僕と一緒に本を書いているサイエンスライターの土屋健さんという方もいます。学年的にはぼくより1つ下なんですけど、福井の発掘の現場で10代の頃に一緒に掘ってて、そっからずっとですね。
丸岡
ずっ友なんですね。
芝原
あ、もう、ずっ友ですね。
丸岡
地域で町ぐるみで本気でお祭りやってるから、大人になっても本気で祭りをやっている!みたいなのと似ている気がしますね。
芝原
そうですね。地元がもともと発掘などが盛んなんですよね。うちの母親も高校時代、地学部を立ち上げていましたし、母親の同級生が、僕の高校時代の地学部の顧問でした。(笑)
他にも地学に関わるみなさんって、中学とか高校の理科の教員をやってるんですけど、それはあくまで表向きの顔であって、週末とかになると研究者と一緒に論文書いてたり、発掘にいっていたりとか。
丸岡
わたし、高校の時に、理系を選択していて、一通り理系教科は学んだんですけど……。その中で「地学って楽しい!!」って思ったことがなかったんで……。砂とか砂利とか、なんとか層とか、「これを覚えて何になるの!?」と思ってた記憶があります。(苦笑)
なので、芝原さんを前にして、失礼だとは思うのですが、地学ってそんなに面白いの?という疑問がありまして。そんなに長年ハマれる魅力って、なんでしょうか?
芝原
わかります、わかります。
これ、今回のテーマの中核にしてもいいかなと思うんですけど、「これただの砂じゃん」とか「泥じゃん」っていうのを突き詰めていくと、実は地球46億年の歴史を刻み込んだものすごい緻密なデータベースになってるんです。地球が勝手に溜め込んだ天然のデータベースと言うか、もうあの、文字通りビックデータなんです。ただの土とか砂が。
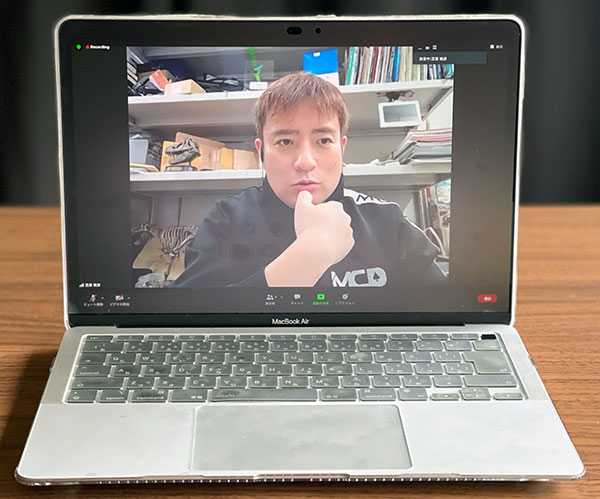
土や砂は地球が溜め込んだ天然のデータベース
芝原
その膨大なデータを分析して、建築とか防災とか環境とか、に役立てているんです。実は、古生物学や地学って、そういう生活に直結してる学問なんです。
この後のお話では
・化石にたどりつくために地層を学んだこと
・化石のために地図の勉強をして、3Dで表示できる地図を作成したり
・微生物の化石を研究し、化石をデータとして扱えるようになったこと
・地質が分かると、水の成分が分かったり、温泉の場所や石油の場所などがわかったりすること
……などなど、現実世界で、地質学や古生物学がどう使われているのか!?のお話がきけました。考えていた以上に、古生物学や地質学は、思いもよらぬところで、大活躍。
そんなお話も含めて、語っていただくのが今回の講演会です。
好きを仕事!にしている芝原さんを講演会の場で直接、解剖しちゃいます!誰もが好きを仕事!にしたいですよね。異なる業種だからこそ、ヒントが多いかもしれないですよ。好きこそものの上手なれ。
ぜひ気軽に聞きにきてください。編集部一同、お待ちしております。
この講演会は2021年7月8日を持ちまして終了いたしました

好きを仕事に!恐竜・地質研究者 編 特撮ヒーローから化石、日本の地形まで!?
オンライン講演会[無料]7/8 17:00開催